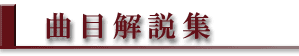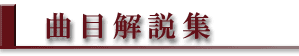|
シューマン 交響曲第2番
|
ヴロベルト・シューマン(1810−1856)
交響曲第2番ハ長調 作品61 (1847年 メンデルスゾーンの指揮で初演)
この交響曲をはじめ珠玉のピアノ曲集、歌曲集のほとんどは、強力な反対を押し切って1840年に結婚した愛妻クララ(1819−1896)への愛と感謝の発露として創作された。 1828、1830、1833(最初の自殺未遂)、1837,1838,1839,1841年と強烈な精神錯乱の発作に襲われ、1844年には鋭物恐怖症も悪化して発作中は記憶も失い、「天職」と誓った作曲は長期間全く出来ない状況に陥った。 数年間の束の間の回復期に書かれた本曲は、天の啓示のような金管(第1楽章冒頭)に始まり、挑戦の決意と愛(第2楽章)、深い憂鬱(第3楽章)、回復し再び天からの霊感を享けられるようになった喜びと希望(第4楽章)などを表現し、第4楽章後半ではベートーヴェンが最愛の人に贈ったとされる最後の歌曲『遥かなる恋人に寄す』(An die ferne Geliebte) が引用されている。 献身的な妻クララ(作曲家で当代一のピアニスト)がその引用を諒解した時の感動は想像に余りある。 またシューマンは真の音楽評論を初めて確立した。 J.S.バッハを再発見したメンデルスゾーン(1809−1847)の功績、青年ブラームス(1833−1897)の才能、『幻想交響曲』で賛否両論を興したベルリオーズ(1803−1869)の真価を、世に広く認識させた見識と勇気の人である。
<第1楽章> Sosutenuto assai - Allegro ma non troppo
「ド」と「ソ」の2音だけで構成され第2、第4楽章でも再現されるシンプルな天の啓示の如き動機を背景に始まる神秘的な序奏では、シューマンが1844年発作の合間に救いを求めるように分析に取り組んだJ.S.バッハのコラール・プレリュード(賛美歌のメロディーを背景に変奏してゆく。例:メンデルスゾーン交響曲第5番「宗教改革」の最終楽章)の書法が採られている。 本体は疾風怒濤、苦悩と挑戦を描き、コーダの決然としたハ長調和音(ド、ミ、ソ)は、ハイドン『天地創造』での「光」の創造時のハ長調和音を想起させ、神の三位一体的臨在と最終楽章での奇跡を予兆している。 3拍子が採られているのもこの場合象徴的であろう。 ちなみに続く第2,3,4楽章もハ音が基調となっているのは異例である。
<第2楽章> スケルツォ Scherzo: Allegro vivace
「スケルツォ」が本来持っていた軽妙さはほとんど姿を消し、疾風怒濤の激しい律動で始まる。 対照的な第1回目のトリオ(本来なら優雅な室内楽)で、スケルッツォの軽妙さを現出させ意表をつく。 第2回目のトリオは、嵐の極限で、突然静かで愛に満ちた弦のコラールとして出現しバッハのフーガの技法で繰り返される。 (最終楽章の「愛の奇跡」も予兆する重要な瞬間である。) 最後は16分音符の律動が戻り終了間際トランペットとホルンが第1楽章序奏の動機を高らかに奏する。 世界中のほぼ全てのオーケストラのヴァイオリン入団試験で、この楽章冒頭が取り上げられる。
<第3楽章> Adagio espressivo
心奥の苦悩と慟哭をあくまでも美しく赤裸々に音楽で吐露した本楽章を、ピアノでクララに弾いて聞かせ終わった際、シューマンは湧き上がる感情の涙に浸り、その後しばらくは作曲できなかったという。暗い道を歩むようなバッハ的対位法(しり取り)の中間部は、ベートーヴェンの交響曲第7番第2楽章(葬送行進曲)のフーガ(死後の魂が歩む様)が念頭に置かれ、心細くおぼつかない足音と深い暗闇があたりを覆う。
<第4楽章> Allegro molto vivace
天からの霊感を再び感じることが出来るようになった奇跡的回復そして献身的なクララへの、歓喜と感謝の音楽である。 上昇音階・音形に満ちた奔流のようなエネルギーが一旦鎮まると、遠く天上から響く愛のコラールが弦に始まり、やがて全宇宙が呼応するようにオーケストラが唱和する。 第3楽章のメロディーは嬉々とした主題に変容して再現され、金管の「ド」と「ソ」の動機は、勝利と喜びのファンファーレとして何度も奏される。 3拍子(第1楽章の拍子)が、コーダで2拍子と同時進行する形で参入し、歓喜は最高潮に達する。 シューマンでしか出来ない純粋で真摯な喜びの世界が宣誓されている。
小松長生
この曲目解説は、2007年9月14日セントラル愛知交響楽団定期演奏会のプログラム用に書かれたものです。
|
Copyright© 2001 Chosei
Komatsu. All rights reserved
無断転載禁止 |
|