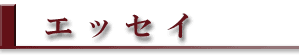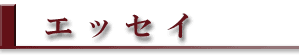| 祖父は明治末まで北前船の船主・船頭をしていた。各地の調度品が並び宮大工によって釘を使わず建てられた三国町崎の家を、幼少のころの私はそう不思議にも思わなかった。両親の判断で保育所には通わず、陣ヶ岡の山と崎の浜辺で、暗くなるまで一人で遊んだ。毎日ずぶ濡れになって帰ってきても、母はただ嬉しそうに笑って着替えさせてくれた。芦原中や三国中の教師だった父とは、週末になると一緒に竹薮で釣竿用の竹を切り、浜のヤドカリを餌に、アイナメやシマダイを釣った。
4歳か5歳のころ、カラヤンが単身来日してN響を指揮するのをテレビで見て魅了され、毎週熱心に見入っていた。それを見た母の「指揮者になりたいの?ほんなら、なんね」という一言をきっかけに指揮の真似を始め、将来指揮者になるんだと決意した。それ以来事あるごとに指揮者の役を買って出て、雄島小2年の学芸会では、「アリとキリギリス」で夏に浮かれるキリギリスたちのバンド(木琴、ハーモニカ、壊れたマンドリンなど)を指揮したりした。父の転勤で福井市の宝永小学校に移ってからも、市の連合音楽会や卒業式で全員合唱を指揮させてもらったのが懐かしい。
|