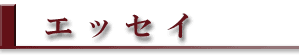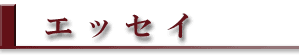|
韓国
|
|
1982年9月私はNY州ロチェスターのイーストマン音楽院大学院指揮科に入学し、実践的な指揮もさることながら、各時代の音楽史、作曲分析法、そして対位法(フーガ等の作曲技法の一つ)の授業に睡眠時間もないほどの日々を送っていた。その対位法のクラスに、既に韓国の大学で教えていて韓国政府の派遣による視察研修の為に留学していた作曲家ユングスン・パク氏がいた。色はあくまでも黒く小柄でやせたパク氏は、どうゆう教え方をするかを観に来ていたから余裕綽々で、落ちこぼれ気味で苦しんでいる私の宿題もさりげなく助けてくれる。パク氏が、私に栄養補給させようと週末アパートに度々呼んでくれて、奥さんの美味しい手料理を食べさせてくれた。彼らの住むアパートのビルの玄関に入ったとたん強烈な韓国料理の匂いが充満していて、「近所からの苦情がひどい」「家内がつくるキムチは世界一」といって、私を息子のように可愛がってくれた。新作の初演指揮をたのまれたり、ロチェスターの韓国教会のコーラスを指揮することになった彼の為に、指揮レッスンをしたりした。後年パク氏の亡き父は抗日運動の英雄であったことを偶然他の人から聞いて、彼ら夫婦の厚意がなおさら身にしみた。あれから丁度20年たって、2002年6月にスーウォン(水原)、ソウルのオーケストラを指揮することになった。
韓国側主催者によると、戦後韓国のオーケストラを指揮する日本人は私が初めて。また過去の両国間の不幸な歴史の生々しさも知るに及んで、私は生まれて初めての不安と緊張を感じながらインチェン(仁川)国際空港に降り立った。カナダのヴァンクーヴァーに住んだことがあるという好青年ハー氏の出迎えを受け、空港からもソウルからも一時間のところにあるスーウォンのホテルにあっという間に着いた.。サッカー場をお見せしようかという親切な彼の申し出を夜更けなので辞退して、近所の大衆カルビ食堂(スーウォンは韓国でもカルビで有名)に閉店間際に一人で飛び込んだ。言葉は余り通じなくても、瞬く間にほとんど無造作にテーブル一杯に皿が並ぶ。客人をもてなすにはテーブルの脚が折れるほど料理を出すという表現が韓国にはあるそうだ。素朴で暖かな笑顔と給仕に、『これだけでも韓国に来て良かった』と、ほとんど涙が出た。
翌日は休みだったので、韓国民族村へ行った。19世紀の装束と村が再現された素晴らしい観光施設だ。その後600ウォン(約65円)でバスにのり、スーウォン駅近くでまたカルビの夕食をとった。3−4人の給仕のおばさん達が、ワールド・カップ用の通訳本を片手に入れ替わり立ち替わり質問し、私はカナダに住んでいて野外コンサートの指揮で来ていると説明した。ホテルに戻ってしばらくすると、フロントから『さっきカルビをお食べになった店が、間違って二重どりしてしまったので、下に御金を返しに来ている』と連絡が入り、驚いて下におりてみると、英語の出来る親類らしい女子学生二人が、1600円相当のお金を返しにバスにのってやってきていた。明日からいよいよリハーサルがはじまる。 ユネスコから世界遺産の指定を受けている華城(数キロの城壁と幾つものの美しい門から成る)の練武台近くに特設野外ステージを設けて、クライマックスには花火を打ち上げるW杯記念日韓友好コンサートは、5000人を超える市民で賑わった。地元スーウォン・フィルと合唱団、韓国(ユンホワン・キム)、イタリア(アレッサンドロ・サフィーナ)、日本(佐野成宏)の3テナー、フィンランドのトランペットの名手 ジョウコ・ハージャンネ氏が出演し、指揮は私とチョン・ミュンフン氏である。3人のテナーはリハーサルのときから和気藹々で、3人揃って歌う『乾杯の歌』では、椿姫等の女性パートを競ってシナをつくって歌いチョン氏を苦笑させる。『オ−ソレミオ』でも、3人の割り振りをちゃんと楽譜に用意してきた私をからかって(テナーは譜面を読まないーーー読めないという説もある)、ゲネプロでわざと出番を交換し合って、驚かせる。
映画俳優並の容姿のサフィーナ氏は、合唱の女性団員達と話し込んでいたからといって、自分の曲のリハーサルに遅れて登場し、汗をぬぐう動作をして私にウインクする。コンサートは冒頭の韓国国歌(チョン氏指揮)からもう熱を帯び、私はハイドンのトランペット協奏曲、『アイーダ』の勝利の凱旋の部分やアリア、チョン氏は『王宮の花火』他を指揮した。ロック・コンサートのような口笛と声援が嬉しかった。コンサート後、一人の年配のご婦人が静かに近付いてきて、「ハワイ生まれの日本人です。この日を待っていました。」とだけ私に言って去っていった。
6月下旬ワールドカップでの自国チーム大活躍で沸くソウルについた。今回は韓国を代表するオーケストラの一つで最古の楽団でもあるソウル・フィルの定期演奏会を指揮するためである。ブラームスの最後のオーケストラ曲『ヴァイオリンとチェロの為の協奏曲』の独奏者には清水高師氏(Vl)とチョン・ミュンワ氏(Vcl)が迎えられている。またストラヴィンスキーの『火の鳥』を締めくくりに指揮する。着いた翌日は準々決勝『韓国ードイツ戦』にあたり、プラザ・ホテルから見下ろせる市庁舎前広場には、何十万という市民が正午過ぎから赤一色で埋め尽くし、大声援を繰り広げている。エレキ・ギターや太鼓のために窓が振動している。ドイツ相手にベートーベン『第九』の替え歌まで繰りだし応援している。凄いエネルギーだ。
ソウル・フィルとのリハーサルは、どんどん伸びていくぞというサッカーで感じられる気概がそのまま反映した、充実感のあるものであった。とりわけオーケストラの奏でるブラームスは重厚で誇りに溢れていて,清麗な清水氏、骨太のチョン・ミュンワ氏の音楽とうまく溶け合っていた。コンサートマスターは米国(インディアナ大)に学び、フルート奏者も私とレコーディングしたエップナー(Fl)と親友であったりして話も弾み、次第に楽員達との距離感が縮まっていった。意外にも『火の鳥』をオーケストラは最近やったことが無いらしく、難曲であることも相俟って、緊迫した猛練習の連続となった。
そもそも言葉ほど当てにならないものは無いし,またプロの団員もくどくど指図されるべきではないとの信念から、私のリハーサルは、最小限の指示だけで、黙々と弾きこむ形となる。しかしながら、『火の鳥』の最後の金管による壮大な一連の和音だけは説明することにした。
「フィナーレは、火の鳥によって魔王の呪文が解け、朝日が差し込むなか魔の宮殿が黄金に輝く教会(ビザンチン様式の金堂)に変容するシーンである。したがって、火の鳥の構成音型からなる金管の和音は、教会の壮麗なオルガンの響きを現出して頂きたい」とお願いした。真の誇りを備えたMatureなオーケストラは、こういうときに違いがでる。ソウル・フィルはブラームスでもみせた深い内面性を遺憾なく発揮し、見事な演奏をきかせた。そして漆黒の暗闇も余すところなく表現するこの曲が、輝くフィナーレで幕を閉じたとき、初めてのソウル・フィルで、この曲を指揮したのは偶然ではなかったのだと、私は指揮台の上で諒解した。拍手はオーケストラがひけた後もしばらく鳴り止まず、音楽家冥利に尽きた。
(2002年6月)

|
Copyright© 2001 Chosei
Komatsu. All rights reserved
無断転載禁止 |
|